浅草で10年 アミューズミュージアム
2019.08.02

今年3月、浅草での10年に幕を下ろしたアミューズミュージアムは、襤褸(ボロ)に触れることができる貴重な美術館であり、古いこぎん刺しや菱刺しの着物も数多く間近に見ることができる唯一の場でもありました。2階の手仕事ギャラリーでは現役作家さんの作品展示販売もあり、こぎん刺しの作家さんには、この場所での作品展開催に憧れた方もいらっしゃるのではないでしょうか。 この10年間で、こぎん刺しは随分認知が広がったと実感します。こぎん刺しをカジュアルに体験できる作家さんの展示会やワークショップなどが見受けられるようになりました。古物として流通するこぎん刺しの価格は10年で数倍に高騰したとも聞きます。こぎん好きの間では、”こぎんブーム”と呼ばれていたりもしますが、このブームを盛り上げた存在として、アミューズミュージアムを挙げないわけにはいきません。青森でも見ることが出来ない数多くのこぎん刺しに触れる場が東京にあったとことは、日本はもとより世界中へこぎんファンが拡大する重要なポイントだったはずです。
 koginbankは5月、引越し直前のアミューズミュージアムを訪ねました。浅草周辺は、10年で人の流れが大きく変わりました。この10年の変化の中で、ミュージアム運営を通じどんなことを感じて来られたのか、また、浅草を離れたこれからのアミューズミュージアムについて館長の辰巳 清さんにお話いただきました。
アミューズミュージアムは、40年に亘って日本のエンターテインメント・ビジネスを牽引してきた株式会社アミューズが運営しています。サザンオールスターズをはじめ、多くの有名な俳優・ミュージシャンが所属する芸能プロダクションです。畑違いとも思える会社が、なぜ青森の文化を展示する美術館を、しかも東京の浅草に作ったのでしょうか?
koginbankは5月、引越し直前のアミューズミュージアムを訪ねました。浅草周辺は、10年で人の流れが大きく変わりました。この10年の変化の中で、ミュージアム運営を通じどんなことを感じて来られたのか、また、浅草を離れたこれからのアミューズミュージアムについて館長の辰巳 清さんにお話いただきました。
アミューズミュージアムは、40年に亘って日本のエンターテインメント・ビジネスを牽引してきた株式会社アミューズが運営しています。サザンオールスターズをはじめ、多くの有名な俳優・ミュージシャンが所属する芸能プロダクションです。畑違いとも思える会社が、なぜ青森の文化を展示する美術館を、しかも東京の浅草に作ったのでしょうか?
「浅草」
当初は、アミューズがアクティブシニア層に向けた知的エンターテイメントを提供する場としてスタートした新事業でした。 ”アクティブシニア”とは、定年後も、趣味やさまざまな活動に意欲的なシニア世代を言います。当時のこの世代は、いわゆる団塊世代。国内人口比率が高く、彼らの一斉退職がによる悪影響が懸念され、”2007年問題”という言葉が当時話題になりました。一方で、リタイアし時間に余裕ができる彼らの新しいライフスタイルには注目が集まりました。”アクティブシニア”という言葉はこの頃から使われだしたようです。 新事業に相応しい場所を全国各地から探していた会長の大里洋吉さんと辰巳さんは、世界の都市ではエンターテイメントと観光が、密接に結びついて発展していることに着目しました。ならば、日本で一番観光客が多い場所、そして自分たちが拠点とする東京からだとどこが良いのだろう…。 そう考えていたところに、大里会長が「これからは浅草だ!」と。 その頃の浅草は、変わらず下町風情溢れる観光名所でしたが、観光客は現在ほど多くはありませんでした。今ではすっかり名所となったスカイツリーはまだ建設前で、名前も決まっていませんでした。京都や奈良の伝統文化に慣れ親しんだ関西人の辰巳さんは、江戸文化にさほど興味もなく、浅草は正直ピンと来なかったようです。でも浅草に通ううちに、大衆芸能が生まれた浅草の風情を感じるようになりました。
間もなく、浅草寺二天門の前に、後のアミューズミュージアムとなる物件が見つかります。でもそこで何をするかは、まだ何も決まっていませんでした。
大里会長 「おまえ、何かアイデアあるか?」
辰巳さん 「美術館したいです。」
大里会長 「あてはあるのか?」
辰巳さん 「ないです。(キッパリ)」
その頃の浅草は、変わらず下町風情溢れる観光名所でしたが、観光客は現在ほど多くはありませんでした。今ではすっかり名所となったスカイツリーはまだ建設前で、名前も決まっていませんでした。京都や奈良の伝統文化に慣れ親しんだ関西人の辰巳さんは、江戸文化にさほど興味もなく、浅草は正直ピンと来なかったようです。でも浅草に通ううちに、大衆芸能が生まれた浅草の風情を感じるようになりました。
間もなく、浅草寺二天門の前に、後のアミューズミュージアムとなる物件が見つかります。でもそこで何をするかは、まだ何も決まっていませんでした。
大里会長 「おまえ、何かアイデアあるか?」
辰巳さん 「美術館したいです。」
大里会長 「あてはあるのか?」
辰巳さん 「ないです。(キッパリ)」
 「美術館がしたい」なんとなく思い付きで出た言葉でした。だから当然展示物なんて何もありません。物件契約が決まっても、この時はまだ美術館が現実になるとは微塵もありませんでした。しかしこの翌日、里帰り中の大里会長から辰巳さんへ電話が。
「お前の美術館にぴったりのコレクション見つけたぞ!」
大里会長は青森市のご出身です。この時、会長は青森で田中忠三郎と出会ったのでした。
田中忠三郎(1933-2013)は青森県の民俗学者で、江戸から昭和にかけての青森の民具の収集・保存をしてきました。襤褸(ボロ)をはじめとする彼のコレクションは2万点に及び、そのうち786点が国の重要有形民俗文化財に指定されています。
ここから、思いつきが”お前(辰巳)の美術館”としてリアルにスタートしました。でも、あまりにも唐突な話に半信半疑の辰巳さんは、すぐに青森の田中忠三郎のもとへ向かいます。倉庫で見せてもらった莫大な物量にはとても圧倒されました。その場で実際に襤褸や土器に触れ、それらの物のパワーのすごさを感じたそうです。
「美術館がしたい」なんとなく思い付きで出た言葉でした。だから当然展示物なんて何もありません。物件契約が決まっても、この時はまだ美術館が現実になるとは微塵もありませんでした。しかしこの翌日、里帰り中の大里会長から辰巳さんへ電話が。
「お前の美術館にぴったりのコレクション見つけたぞ!」
大里会長は青森市のご出身です。この時、会長は青森で田中忠三郎と出会ったのでした。
田中忠三郎(1933-2013)は青森県の民俗学者で、江戸から昭和にかけての青森の民具の収集・保存をしてきました。襤褸(ボロ)をはじめとする彼のコレクションは2万点に及び、そのうち786点が国の重要有形民俗文化財に指定されています。
ここから、思いつきが”お前(辰巳)の美術館”としてリアルにスタートしました。でも、あまりにも唐突な話に半信半疑の辰巳さんは、すぐに青森の田中忠三郎のもとへ向かいます。倉庫で見せてもらった莫大な物量にはとても圧倒されました。その場で実際に襤褸や土器に触れ、それらの物のパワーのすごさを感じたそうです。
 以前はタレントマネジメントの仕事もしてきた辰巳さんは、モノ以上に人に興味を感じます。2万という莫大な数をコレクションする田中忠三郎という人間を会った瞬間から面白いと感じ、彼の魅力を打ち出す美術館にしたいと思いました。そして、浅草に集まる人は、多かれ少なかれ「和」の文化に浸りたいと思っているはず。ならば、このコレクションで襤褸のミュージアムをやろう!と。
思い付きに奇跡的な偶然が重なり、物件契約から3日のうちにアミューズミュージアムの構想が出来上がりました。
以前はタレントマネジメントの仕事もしてきた辰巳さんは、モノ以上に人に興味を感じます。2万という莫大な数をコレクションする田中忠三郎という人間を会った瞬間から面白いと感じ、彼の魅力を打ち出す美術館にしたいと思いました。そして、浅草に集まる人は、多かれ少なかれ「和」の文化に浸りたいと思っているはず。ならば、このコレクションで襤褸のミュージアムをやろう!と。
思い付きに奇跡的な偶然が重なり、物件契約から3日のうちにアミューズミュージアムの構想が出来上がりました。
美術館つくるぞ!
 4月に契約建物の使用が始まり、当初は会長から5月の三社大祭にオープンをと言われました。でも、美術館のオープンには工事だけでなく、様々な行政手続きが必要で、一般的には準備に2年かかります。そこをアミューズミュージアムは、最短で半年後の10月オープンを目指し、準備にとりかかりました。
辰巳さんは、展示計画を専門家にお願いしようと考えていました。しかし、知人のアートプロデューサーに、「辰巳くん、自分でやりなよ!」と言われます。学芸員の資格も知識も無い自分には到底無理だと思っていました。
「大丈夫!できる、できる!だって忠三郎コレクションに一番愛情持ってるの辰巳君でしょ。」
タレントマネジメントの仕事では、マネージャーがタレントに一番愛情を持っていなくちゃいけない。だからこそ、タレントのディレクションができるのだと、仕事の中で教えられてきました。そうか、美術も同じなんだとこの言葉で気づきました。だったら自分にもできるかもしれない。誰に頼んでも、最終判断は自分がしなくてはいけないのだ。ならば最初から自分でやろう。
4月に契約建物の使用が始まり、当初は会長から5月の三社大祭にオープンをと言われました。でも、美術館のオープンには工事だけでなく、様々な行政手続きが必要で、一般的には準備に2年かかります。そこをアミューズミュージアムは、最短で半年後の10月オープンを目指し、準備にとりかかりました。
辰巳さんは、展示計画を専門家にお願いしようと考えていました。しかし、知人のアートプロデューサーに、「辰巳くん、自分でやりなよ!」と言われます。学芸員の資格も知識も無い自分には到底無理だと思っていました。
「大丈夫!できる、できる!だって忠三郎コレクションに一番愛情持ってるの辰巳君でしょ。」
タレントマネジメントの仕事では、マネージャーがタレントに一番愛情を持っていなくちゃいけない。だからこそ、タレントのディレクションができるのだと、仕事の中で教えられてきました。そうか、美術も同じなんだとこの言葉で気づきました。だったら自分にもできるかもしれない。誰に頼んでも、最終判断は自分がしなくてはいけないのだ。ならば最初から自分でやろう。
 そして、コンサートの曲順を考える要領で展示の順番を決め、舞台美術の知識と経験を活かし、背景や光の当て方で演出を考えました。特にこぎん刺しに比べて襤褸は、普通に光を当てても、ただのボロ雑巾にしか見えません。だから反射光を当ててみたり、光る什器の上に乗せてみたり工夫が必要でした。
時間はありませんでした。襤褸の全体コンテクスト(背景)を伝える手段として、同時並行で編集していた、田中忠三郎自叙伝のテキストを活用しました。自叙伝は田中氏の希望で準備していたもので、伝記にありがちな時系列を追うことにこだわらず、短めのストーリーを束ねて作っていました。コンテクストを伝えるキャプションとして展示に取り入れるにはちょうど良いと思いました。しかし、実際に並べてみるとテキストが長く、従来の美術館の6〜7倍の量になりました。
そして、コンサートの曲順を考える要領で展示の順番を決め、舞台美術の知識と経験を活かし、背景や光の当て方で演出を考えました。特にこぎん刺しに比べて襤褸は、普通に光を当てても、ただのボロ雑巾にしか見えません。だから反射光を当ててみたり、光る什器の上に乗せてみたり工夫が必要でした。
時間はありませんでした。襤褸の全体コンテクスト(背景)を伝える手段として、同時並行で編集していた、田中忠三郎自叙伝のテキストを活用しました。自叙伝は田中氏の希望で準備していたもので、伝記にありがちな時系列を追うことにこだわらず、短めのストーリーを束ねて作っていました。コンテクストを伝えるキャプションとして展示に取り入れるにはちょうど良いと思いました。しかし、実際に並べてみるとテキストが長く、従来の美術館の6〜7倍の量になりました。
 そこで、文章を読みやすい環境にするためにBGMを流しました。文章を読む時は音があると集中しやすいものです。それに従来の美術館にありがちな無音の空間では声を発するのも憚ります。でも展示を見ながら会話のできる美術館にも辰巳さんはしたかった。
まず、襤褸の第一展示室はボサノバ。これは辰巳さんが留学先のブラジルで見た、彼らの生活にある夏のカーニバルに、青森のねぶたと通じる解放感を感じたからだそう。また、第4展示室では鈴虫の声。青森県下北地方では鈴虫をボドツゲと呼びました。昔は鈴虫の声とともに夏が終わり、襤褸を縫い始め、冬支度をはじめたものでした。鈴虫は襤褸(ボロ又はボド)の準備をする合図でもありました。
そこで、文章を読みやすい環境にするためにBGMを流しました。文章を読む時は音があると集中しやすいものです。それに従来の美術館にありがちな無音の空間では声を発するのも憚ります。でも展示を見ながら会話のできる美術館にも辰巳さんはしたかった。
まず、襤褸の第一展示室はボサノバ。これは辰巳さんが留学先のブラジルで見た、彼らの生活にある夏のカーニバルに、青森のねぶたと通じる解放感を感じたからだそう。また、第4展示室では鈴虫の声。青森県下北地方では鈴虫をボドツゲと呼びました。昔は鈴虫の声とともに夏が終わり、襤褸を縫い始め、冬支度をはじめたものでした。鈴虫は襤褸(ボロ又はボド)の準備をする合図でもありました。
 アミューズミュージアムでは展示物を実際に触れることもできました。これは、辰巳さんが初めて田中忠三郎の倉庫で襤褸に触れた感動がきっかけです。布のゴアつきや重さが、手で触れることで頭が納得する以上に腹に落ち、実際に触れると、より多くの情報を五感で得られると感じました。この体験を提供することにはリスクを伴います。コレクション所有者の田中氏には、恐々提案してみました。ところが即決、「面白い!」と言ってくれました。それでも最初は正直不安はあったそうです。しかし、来場者はコアなファンが多かったこともあってか、心配していた事故は起きませんでした。
アミューズミュージアムでは展示物を実際に触れることもできました。これは、辰巳さんが初めて田中忠三郎の倉庫で襤褸に触れた感動がきっかけです。布のゴアつきや重さが、手で触れることで頭が納得する以上に腹に落ち、実際に触れると、より多くの情報を五感で得られると感じました。この体験を提供することにはリスクを伴います。コレクション所有者の田中氏には、恐々提案してみました。ところが即決、「面白い!」と言ってくれました。それでも最初は正直不安はあったそうです。しかし、来場者はコアなファンが多かったこともあってか、心配していた事故は起きませんでした。
浅草から世界へ
2009年10月に半年の準備を経て無事にオープンしました。オープン当初は電車の吊り広告などのプロモーションを積極的に行っていましたが、展示内容の専門性が強すぎるためか、効果は得られませんでした。なかなか認知は広がらず、人も集まらず、プロモーションの余裕はなくなり、お金もなくなり…。窮地に追いうちをかけるように2011年3月の東北大震災。あの頃は浅草に限らず東京の街は人がまばらでした。 しかしその頃から、コアなファンに知られるようになりました。2012年にはスカイツリーが開業し、インバウンド政策で浅草は外国人観光客が増えました。世間ではSNSの発達で個人の発信がすごいスピードで拡散されるようになり、それらが影響してか、アミューズミュージアムにはクリエイティブな人や学生の来館が増えてきました。学校の課題として利用されたり、辰巳さん自身にも教育機関から講演依頼が来るようになりました。
第一線で活躍するファッションデザイナーも、ここを訪れていたようです。2013年から立て続けにハイブランドが襤褸を取り入れたコレクションを発表しています。2013年のルイ・ヴィトン、2014年のアルチュザラ、2015年はコム・デ・ギャルソン。国内では、2015年にボロや刺し子のテキスタイルでメンズアパレルを展開するブランドkuon(くおん)が登場しました。辰巳さんはファッション紙記者から、当時ルイ・ヴィトンのデザイナーだったキム・ジョーンズはここに脚を運んでいたと聞いています。アミューズミュージアムの10年間の来場者のうち、4割は外国人でした。キルト作家や、テキスタイルデザイナー、クリエイター志望の学生など、来日目的がアミューズミュージアムだという人も、少なくありませんでした。当初はアクティブシニアに向けた場所だったのが、いつのまにか若い、新しいクリエイティビティに影響を与える存在になっていました。今では襤褸は”BORO”の綴りで世界中に認知されています。
しかしその頃から、コアなファンに知られるようになりました。2012年にはスカイツリーが開業し、インバウンド政策で浅草は外国人観光客が増えました。世間ではSNSの発達で個人の発信がすごいスピードで拡散されるようになり、それらが影響してか、アミューズミュージアムにはクリエイティブな人や学生の来館が増えてきました。学校の課題として利用されたり、辰巳さん自身にも教育機関から講演依頼が来るようになりました。
第一線で活躍するファッションデザイナーも、ここを訪れていたようです。2013年から立て続けにハイブランドが襤褸を取り入れたコレクションを発表しています。2013年のルイ・ヴィトン、2014年のアルチュザラ、2015年はコム・デ・ギャルソン。国内では、2015年にボロや刺し子のテキスタイルでメンズアパレルを展開するブランドkuon(くおん)が登場しました。辰巳さんはファッション紙記者から、当時ルイ・ヴィトンのデザイナーだったキム・ジョーンズはここに脚を運んでいたと聞いています。アミューズミュージアムの10年間の来場者のうち、4割は外国人でした。キルト作家や、テキスタイルデザイナー、クリエイター志望の学生など、来日目的がアミューズミュージアムだという人も、少なくありませんでした。当初はアクティブシニアに向けた場所だったのが、いつのまにか若い、新しいクリエイティビティに影響を与える存在になっていました。今では襤褸は”BORO”の綴りで世界中に認知されています。
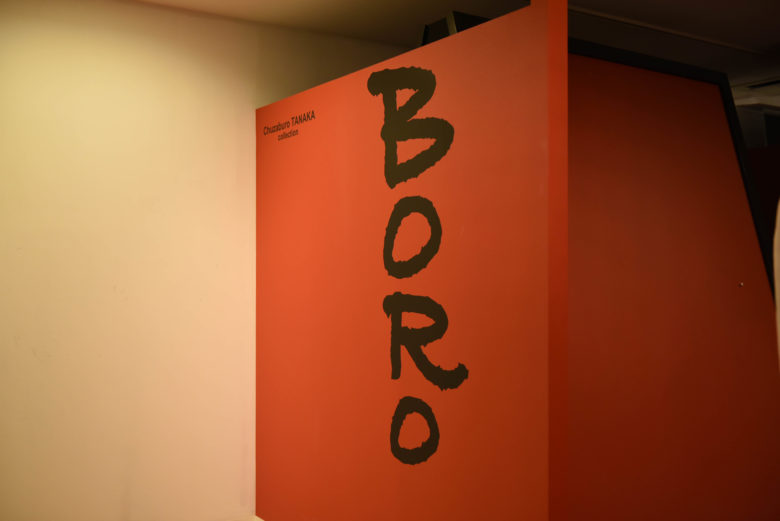 現在アミューズミュージアムは、6月のオーストラリアを皮切りに、ワールドツアーの最中です。襤褸は日本を飛び出しました。昨年の閉館発表以降、各国からオファーが届き今回のツアーが実現しました。オーストラリアでは、オーストラリアンキルトやアボリジニーアートとの展示を行いました。この後は、北京、ニューヨークでの開催が決まっています。このツアーでは、各国のテキスタイルと比較展示をしたいと辰巳さんは考えているそうです。今も新たな国からオファーが来ているそうなので、近いうちにワールドツアーに新たな開催地が加わるかもしれません。
このツアーが終わった後は、再び日本の新たな場所で再開することが決まっています。いろんな国から刺激を受けて帰ってくるフォークロアテキスタイルの襤褸が、どんな新しい魅力を見せてくれるのか、今度はどこにムージアムが帰還するのか、新しいアミューズミュージアムが今からとても楽しみでなりません。
アミューズミュージアムの今後のスケジュールはオフィシャルサイトで随時更新されます。
アミューズミュージアムオフィシャルサイトはこちら
現在アミューズミュージアムは、6月のオーストラリアを皮切りに、ワールドツアーの最中です。襤褸は日本を飛び出しました。昨年の閉館発表以降、各国からオファーが届き今回のツアーが実現しました。オーストラリアでは、オーストラリアンキルトやアボリジニーアートとの展示を行いました。この後は、北京、ニューヨークでの開催が決まっています。このツアーでは、各国のテキスタイルと比較展示をしたいと辰巳さんは考えているそうです。今も新たな国からオファーが来ているそうなので、近いうちにワールドツアーに新たな開催地が加わるかもしれません。
このツアーが終わった後は、再び日本の新たな場所で再開することが決まっています。いろんな国から刺激を受けて帰ってくるフォークロアテキスタイルの襤褸が、どんな新しい魅力を見せてくれるのか、今度はどこにムージアムが帰還するのか、新しいアミューズミュージアムが今からとても楽しみでなりません。
アミューズミュージアムの今後のスケジュールはオフィシャルサイトで随時更新されます。
アミューズミュージアムオフィシャルサイトはこちら
インタビュー:koginbank編集部 text:石井 photo:鳥居


